梨を食べられる幸せ!
こんばんは。日が暮れるのが早くなってきたのと、朝・夜の涼しさで秋がすぐそこまで来ているなと季節の変わり目を体で感じている聖士です。30℃越えの日々が続いたことで20度前半の心地よい気温が少し寒くも感じてしまいます。来年には40℃を超えた日を『酷暑日』と名付けるというようなニュースを見かけました。
人間の体もどうにかなってしまいますが、野菜や果物にも相当影響が出ているらしいですね。先日『タモリステーション』という番組では、異常な日本の夏 緊急スペシャル と題して二時間ほどの放送がやっていました。大雨の災害、農作物の被害、気温が上がることで近い将来生活が変わってしまうなど、今までの生活が普通でなくなってしまう怖さを感じました。
夏野菜やスイカや桃、梨などの夏が旬のフルーツは僕は大好きなんです。毎年父の知り合いの梨農家さんから梨を購入させていただいているのですが、今年はこの暑さで大きく成長せず出荷できるか厳しいなどという情報が少し前に入ってきたんです。
毎年楽しみにしている果汁たっぷりで美味しい梨が今年は食べられないのかと残念に思っていました。しかし、先週届き、美味しいうちに家族みんなでいただきました!

大きくてみずみずしい美味しい梨を今年もたくさん食べることができて幸せです。しかし、このまま地球が沸騰化していくと近い将来色々な農作物が取れなくなり大好きなものが食べられなくなってしまう可能性も大いにあります。ですので、ひとりひとりが小さなことから地球を守る行動を心掛けて生活していくことが本当に重要になってくると思います。タモリステーションでも言っていました。「選挙と同じで国民一人の一票で大きく日本が変わるように、ちょっとした行動を皆がやれば地球も大きく変わりますよね」。全くその通りだと感じました。節電・節水などできることから始めて、美味しい食べ物を救いましょう!
間取りの方程式!
先週から井野設計塾が始まり、早速設計課題に取り組み始まています。まだ設計をしたことがないので、まずはある本を読み直すことから始めました。その本を手に取ったのは約3カ月前です。
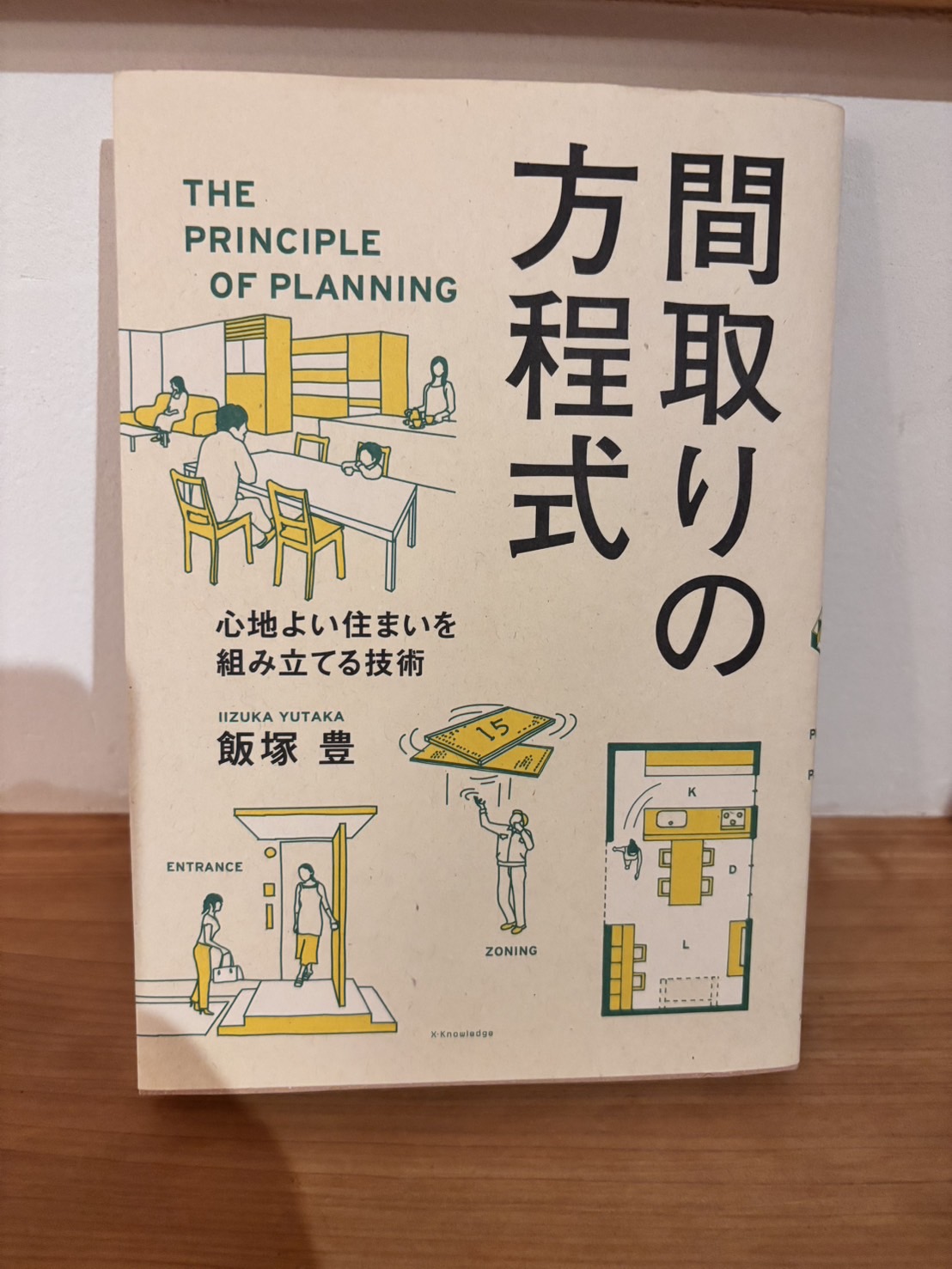
この本との出会いは、今年の6月に東京で開催された勉強会に参加した時、i+i設計事務所代表の飯塚豊さんに偶然お会いしたことでした。
まだ設計をしたことがない僕にとって絶対役に立つからとこの本をおすすめしていただき、「どんなことが書いてあるんだろう?早く読みたい!」と心を熱くし、帰り道に早速ネットで購入したのを思い出します。
この本では、家を豆腐(四角い箱)に例えて一部を切り取ったり、伸ばしたり、凹ましたり。四角を基本とすることで屋根がキレイにかかり見た目も間取りもスッキリするということなどが書かれています。その他にも、敷地条件に合わせた建物・駐車場・庭の配置もとても重要だということもです。
この本を読む前は、「まずは間取りを決めなけれな始まらない!」と思っていましたが、そうすると複雑な屋根の形をした家になってしまうんです。街を歩いているとたまに見かけますよね。
『シンプルな切妻・片流れの屋根』そんな家面白くないじゃん?
そんなことはありません。複雑な屋根だと雨仕舞や納まりが難しくなり雨漏りのリスクが上がりますが、シンプルであれば工事がしやすくなりますし、見た目もスッキリするんです。ですので、まずは敷地を見てボリュームと窓の位置を決め(どこを見せるか、どこに抜けを作るか)、LDK、寝室、水廻りなどのゾーニングへと進んでいきます。シンプルにすれば断熱気密性能も安定してきますし、構造的にも安定します。
今思えば大学の設計の授業でも先生たちからそう教わりました。課題は住宅ではなかったのですが、紙粘土を使ってボリューム出しをしましょうということから始まり、その後コア(エレベーターやトイレなど)とパブリックゾーンのゾーニング、それが決まったら細かな部屋の配置を決める。大きな建物でも住宅でも設計の考え方って同じなんですね!
ボリュームやゾーニングが決まれば生活動線を踏まえた間取りの決定はある程度自由が利くらしいのです。僕はまだその段階まで行っていないのでまだ難しいかもしれませんが、色々な経験を通してこの本を参考に自分なりの設計を身に付けていきたい思っております。設計するうえで大切な要素が詰まっている本だと感じたので、困ったときは何度も読み返すようにしたいと思います!
ブログを読んでくださりありがとうございます。
松島匠建㈱ 松島聖士